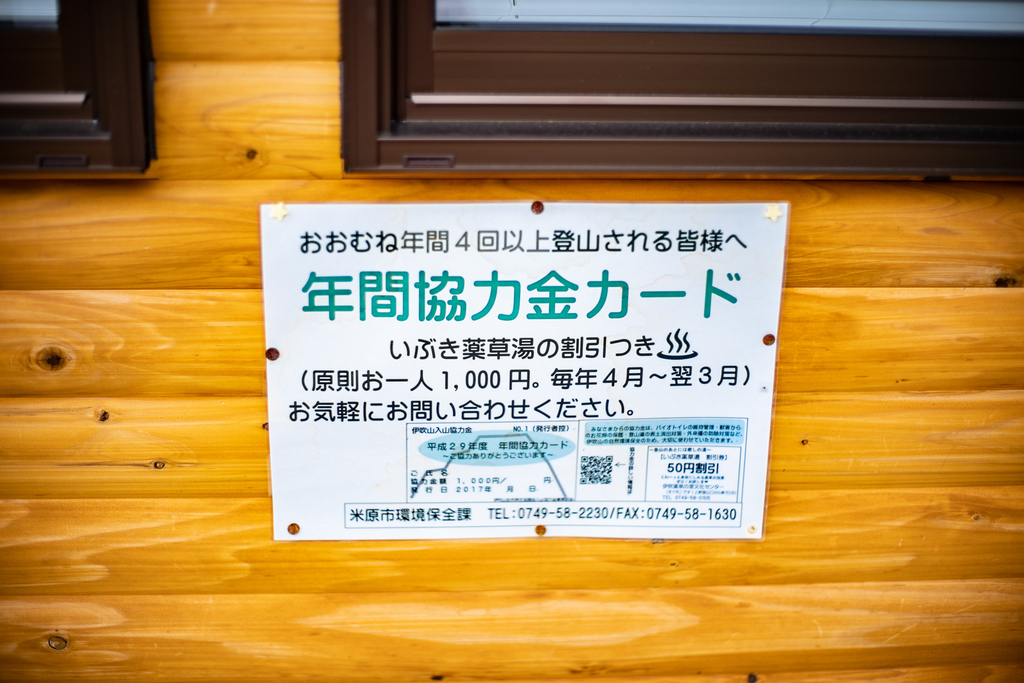山頂直下
もう、頂上が見える。前回は右手の林のさらに向こう側を直登した。やはり前回は、少し変わったところを直登したようだ。あれはあれでよかった。
ここから急な斜面になり、ただただ足元に気をつけて登っていく。

8合目も四捨五入すれば10合目だ。着いたも同然だ。
頂上についてしまえば、後は降りるだけだし、登山は、頂上よりも、もしかしたら、このあたりが一番ウキウキするのかもしれない。昔、子供の頃に作ったプラモデルも、描いた絵も、作っている過程が楽しく、完成してしまうと、ふっと興味がなくなることがあった。今でもそれは継承されていて、自分が撮った過去の写真にはあまり興味がないかもしれない。写真も作り上げていく中で必要な行程を苦労して昇華した後に残されたものである。
いや、そんなことよりも、今は頂上目指して一歩一歩だ。岩場を登りやすいルートで乗り越えていき、やっとこさ、柵のある頂上の稜線に出た。
前回
今回は、風もないいい天気。てくてくとヤマトタケルノミコトに向かって歩いていく。
そう、伊吹山は頂上付近は平らなので風がなければとても心地よい。
伊吹山山頂へ
真っすぐ歩いていくと、小さな祠が見えた。いつもは真っ白になっているはずなのだが、今年は微妙な雪のお化粧だ。

とはいえ、気温は低く、寒い。
景色は素晴らしく、白山の向こうの山々が見える。
ヤマトタケルノミコト、一応挨拶して、その場を離れる。


スカッと抜ける青空ではないにしても、なかなかのいい天気だ。
しかも平日なのでほとんど人がいない。後から数人が来ただけだ。


ここでお昼にしようと思っていたのだが、ちょっと寒いし、まだ時間もあるので少し降りてからご飯にすることにした。無理やり頂上で食べる必要なんかない。いつから「お昼は山頂」ということになったのであろうか。
というわけで、しばらく景色を堪能した後、下山。

稜線に出た場所から、直登ルートを覗き込む。ちょっとこっちで降りたい気もする。
なんだか、くぼみが多そうなので、やはり来た道を降りることにした。安全第一。
伊吹山の下山は景色が良いので気持ちいい。

次第に近くなる麓は少しさみしいが、それでも抜けの良い景色を眺めながら歩けるのは良い。
登ってきた道にかかっていた時間に比べると、下りはあっという間だ。しかも疲れない。こういう時、息を切らしながら登っている人とすれ違う時、心の底から「がんばれ」と思ってしまう。ほんとにがんばってほしい。

下山
積雪期の伊吹山は今期はこれで最後だろう。じっくり味わいながら下山する。
降りるペースは登るペースよりも当然速いので、それにともなって雪の量がどんどん減っていくのがより、わかりやすい。悲しいかなこれも現実。そうか、雪山は登る時は、空きから冬に、そして下に降りるごとに春になっていく気持ちが味わえると思うと、なかなか良い。

と、のほほんと思っていたら、一気に避難小屋まで降りてきた。
ちょうど登る人も相まって、少し賑やかだ。ひとりぼっちもいいけど、やっぱり賑やかなのは良い。
ランチはカップヌードル
避難小屋の中に入るには靴を脱がなければならないので、外でご飯を食べることにした。
相変わらずカップヌードルだ。
お湯を沸かし直して、熱々の100度のお湯をカップに注ぎ入れる。
三分待つ。たかが三分、されど三分。

いつものように五臓六腑に染み渡る塩分だ。さすが日清。
今期最後の雪伊吹
ここからはアイゼンを外しても大丈夫な感じ。
今年は全く積もらなかった伊吹山、来年、期待してますよと。
とはいえ、伊吹山は標高の割には積雪が多い。なぜかはわからないが、いつも標高以上に雪をかぶっていただいているので、今年が少ないからと言って、文句は言えない。
そう、感謝の念を大地に送りながら、下山する。
しだいに緩んできた地面、やはりな。行きは硬かった地面がすっかりゆるんでいる。
今回、Goproで録画しながら登山し、そして、見たことや感じたことを喋りながら録画し、後日こうして書き起こすという、荒業をしているのだが、どういうことか5合目辺りから、山頂、そして下りの5合目まで、動画ではなく早回しのタイムラプスで撮ってしまっていて、まったくの早足、かつ、無音で録画されてしまった。道中、ブツブツと独り言を言っていたのが、ほんとにただの独り言になってしまった。
振り返ると、少ない雪で無理やりヒップソリをしている人たちがいた。賑やかで良い。
ここからはアイゼンを外しているので、ショートカットルートは行けない。
そしてアイゼンを外した直後は、ついついアイゼンを付けている気持ちになってしまって、滑りそうになる。気をつけねば。重心に気をつけて歩く。
アイゼンを付けている時は、つけてないと思え。といったところか。試合は練習と思え、練習は試合と思え、と似ているようで、にていない。
それとストックは、雪と岩のミックスの時は変にカチッとハマってしまって抜けにくくなる時がある。後ろに残されて転けそうにならないように気をつけないといけない。
大きな溝の通り道がある。これに入らないように上の方を歩く。この溝は、そもそも道なのか、なんなのか、流れている雨水がつくったのかもしれない。その土手を歩いたほうがはるかに歩きやすい。美川憲一が「端っこ歩きなさいよ」といったのはあながち間違いではなかったのかもしれない。
柔らかくなった道だけでなく、きもち行きよりも雪が溶けたように思うが、どうだろう。少し悲しい。向かいの霊仙山も今年は雪が少ない。
振り返ると伊吹山、そこに数人の登山客が見える。もうすっかり人は小さくなった。
降りるごとに雪よりも石のごろごろが増えてきた。
下りで滑りやすいのはホント勘弁してほしい。あるいやすい場所を見つけながら降りていく。トレランの人はこんなところも走って降りるのだろう、すごい。
アイゼンの外し時、これもまた難しい、一旦外してまた必要になった時の、再度つける面倒くささ、を考えると、ギリギリまでつけておきたくなる。登ってるときに、すれ違いで降りる人たちだけがアイゼンをつけているのは、そういった理由もあるのかもしれない。下りだからというのが大きな理由だろうが。
伊吹山は全体を通してなだらかな斜面なので、歩いている割には高度が上がらない。大きな岩場を登る山は一気に高度が稼げるが、なだらかなジグザグの山道の山はあまり変わらない。
下りはトレッキングポールが役に立つ。特に石がゴロゴロしてる時のバランスは取りやすい。登りより、下りがとても役に立つ。

ちなみに私見だが、六甲山はトレッキングポールは1本というのが良い。たまにある岩場や急な斜面を登るのに手も使うから、片手は開けておいたほうが登りやすい。トレッキングポールは、やはり「トレッキング」に適している。
下りで気をつけないといけないのは、こけないことだ、一気にどろどろになってしまう。
れいのシカの赤い血の道に来た。もうこんなところか、やはり下りは速い。
たまに銃声が聞こえていたが、あれから、また駆除されていたのだろうか。害獣であるシカはただ生きているだけであって「へへへ、俺達は悪の手先だぜ」と思っているわけではない。人間の社会生活に悪永久を与えてしまっているだけである。牛や豚を飼育して食べているのに。なにか不思議だ。かといってそして、野生のシカを狩るのは、ややむごいかなと思ってしまう気持ちもある。でも、養殖の鯛を食べるのは普通で、天然の鯛を食べるのはひどい、と思ったことはない。野生のたいとは言わない。天然と野生は違うのか?野生の鯛、なんかすごい味がするように思えるが、天然という意味と変わらないはずだ。天然のシカ、なんだか希少価値のある名前になってしまった。と、どうでも良いことを考えているうちに、結構降りてきた。3合目か4合目ののトイレのある場所だ。ここは昔マウンテンバイクでレースをしに何回か来たことがある。クロスカントリーに出ていたが、あれはほとんど自転車を担いで走る借り物競争のようだった。たしか、自分の自転車に「FOR SALE」と書いて売りに出しながらレースに参加している外国人がいたのを覚えている。
正面にロープウェイの跡地を見ながら左の通路を降りていく。
この通路まではまだ雪があるが、この先はもう雪はないはずだ。来年よ、積もっておくれ伊吹山。と一句。
やはりここからはただの秋のような道を降りていく。
ここからだんだんと靴底に泥が積もっていく。たまにサッカーのキックで泥を吹き飛ばす。そうすると、少し足が軽くなる。
それを繰り返しながら降りていく。
泥と石のトラップに気をつけながら、私は降りていった。
1合目までは泥がきつかったが、樹林に覆われたジグザグの道は、案外乾いていて、浮石に気をつけていけば、案外楽に降りれた。
コーラを飲む。
少し疲れた体がギュッと生き返る。ベンチプレスをしていて、もうだめだというときにコーラを飲むと、もう一本いける様になるのだから、コーラはなかなかすごい。
今回は、足をくじくことなく、登山口に帰ってきた。

次回来るのはいつだろう、せっかくだからお花が咲いていて涼しいときにまた来よう。
バスの時間まで、もう少しあるので、いつものようにキレイな湧き水で靴などを洗う。
荷物をまとめて、下のバス停でぼーっとしていると、ちょうど良いタイミングでバスが来た。
乗ったのは当然ながら私一人。
冬の終わりを感じれる登山だった。
おしまい。